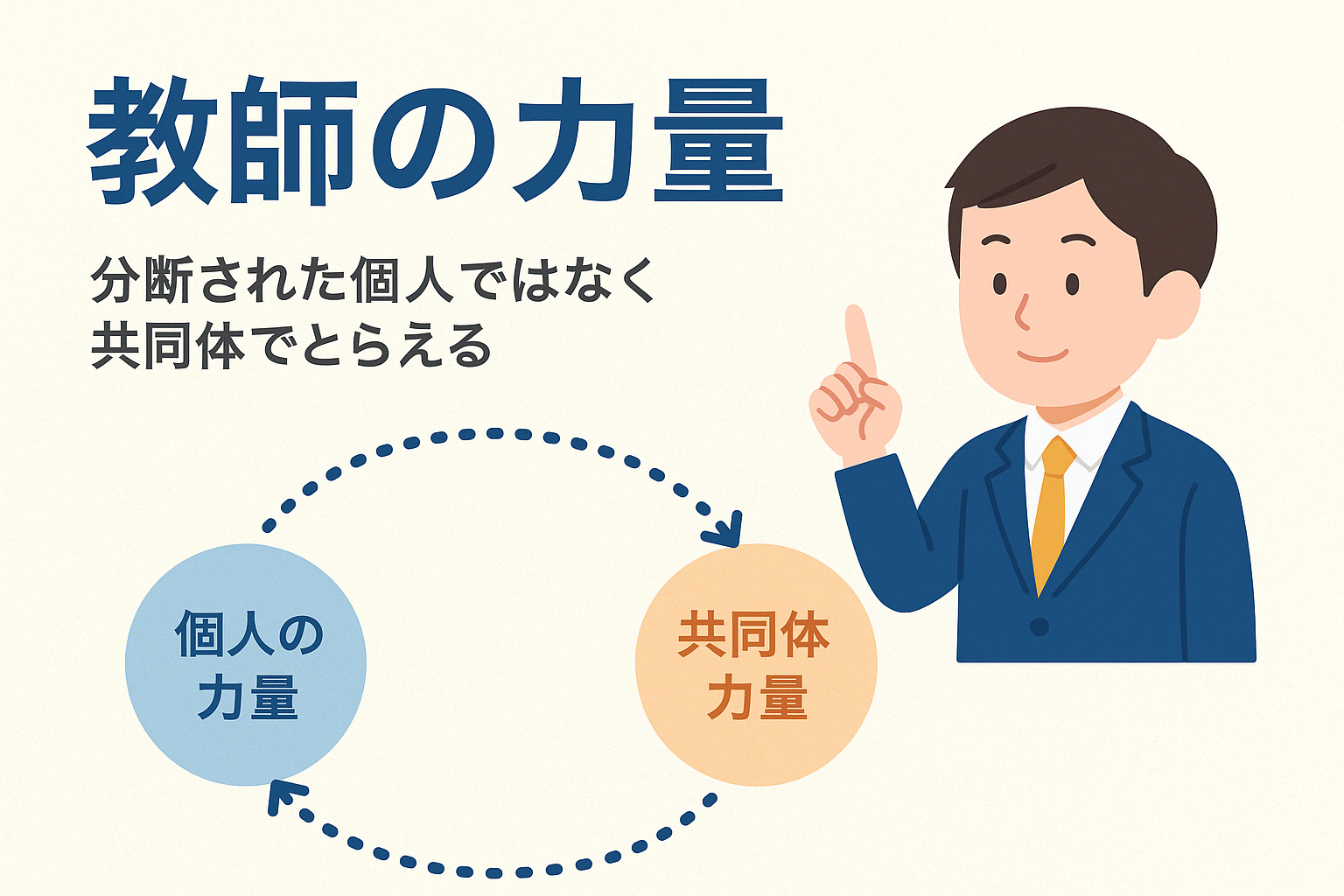☀️はじめに
おはようございます。
昨日はまるで冬のような冷え込み。夜の空気がひんやりして驚きましたが、週末には一転して25度超えの予報も。
気温差の大きい季節、体調管理にはくれぐれもお気をつけくださいね。
さて、今日のテーマは「教師の力量とは何か」です。
🧩「教師の力量」ってなんだろう?
「教師の力量」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?
- 指導案をロジカルに書ける力
- 子どもの前で流れるように授業を展開する力
- 子どもと信頼関係を築ける人間力
いずれも大切で、現場でもよく語られるポイントです。
でも…本当にそれだけでしょうか?
💭若い頃の私と“力量”への違和感
少し昔話をさせてください。
私が若手の頃。
提出した指導案に対して、毎回たくさんのご指摘をいただいていました。
「ここ、ねらいと活動がズレてるんじゃない?」
「この発問だと子どもは広がらないかもね」
「この資料、ちゃんと読んでる?」
正直、内心ではドキドキしていましたが、同時に「これが修業なんだ」と受け止めていました。
そしてある時期から、こう考えるようになったんです。
「もう“突っ込まれない”指導案を書けるようになりたい」
「“よく書けてるね”と言われたら一人前かも」
その思いをバネに、力をつけてきた部分もあると思います。
🤔…でも、昨日ふと気づいたこと
昨夜、何気ない瞬間に、こんな疑問が湧いてきました。
「“突っ込まれないようにする”って、正しい方向なんだろうか?」
「突っ込まれる力」を“自分の力”とどう見るか?
ふと思ったのです。
“突っ込みを受ける”という行為そのものを、自分の力量のなさとしてしか見ていなかったけれど……
実はそれ、「力のつながり」そのものではないか?
つまり、「突っ込まれる関係性」があるということ自体、
・相手が自分に関心を持ってくれていること
・共に授業をよくしようとする営みに参加できていること
・そのやりとりの中で、実は“共に育っている”こと
これらを含めたうえで、「力量」というものを見直したほうがいいのではないか?と、強く思ったんです。
🌐 共同体で見る“力”という視点
私たちが「力量」という言葉を使うとき、
どうしても“個人のスキル”や“自分一人の腕前”という文脈で語りがちです。
でも、例えば指導案検討会という場で、
- 書いた人
- 指摘する人
- 議論を聞いている人
この全体が「ひとつの学びの共同体」として動いているのなら、
誰かの力=みんなの力という見方も成り立つのではないでしょうか?
🧭 OECD「共同体エージェンシー」の視点
この視点は、OECDの「ラーニング・コンパス」でも重要なキーワードとして出てくる
Community Agency(共同体エージェンシー)にも重なります。
“能力は個人の中にだけあるのではなく、関係の中にある”
という考え方。
つまり、「力量とは“関係性の中にある力”でもある」という見方です。
🔄 力の見方が変わると、行動が変わる
この見方に立つと、
「突っ込まれないようにする」から
→「対話や修正が生まれる関係に価値がある」に変わっていきます。
そして何より大事なのは、
他者からの意見を受け止めながら、自分を開いていく勇気こそが“力量”そのものなのかもしれない、ということです。
🧠 まとめ:力は、“つながり”の中にある
「力量」という言葉に対して、これまではどこか“試される感じ”がありました。
けれど、見方を少し変えるだけで、それは「支え合いの中で育っていくもの」に変わっていく。
- 指導案に意見をもらえること
- フィードバックが飛び交う場があること
- 自分を開いてやりとりできること
それらすべてが、「教師の力量」なのだと、今は思っています。
☕さいごに
この見方は、これからの教育現場にとって、とても大切な考え方になると私は感じています。
「誰かの力」ではなく、
「わたしたちの力」として教育をとらえる。
そんな視点が広がっていくことを、心から願って。
今日もすてきな一日をお過ごしください🌿
🎁この記事は、こんな方におすすめです
- 指導案検討会や授業研究に悩んでいる先生
- フィードバックにどう向き合えばいいか迷っている方
- 「力量」や「エージェンシー」に関心のある教育関係者