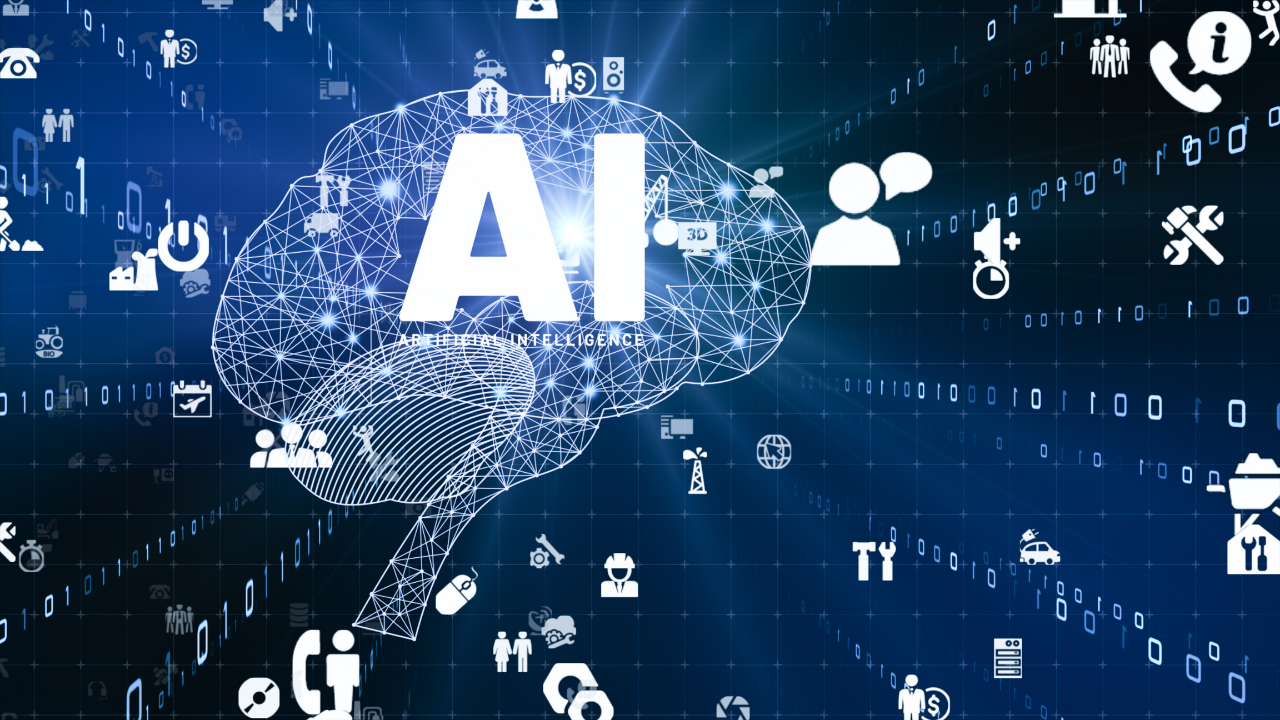はじめに
ChatGPTやGeminiに代表される生成AIが登場し、教育や研究の在り方に大きな変化をもたらしています。論文や教材研究もAIで作成できる時代に突入しつつある今、私たちは「AIをどう使うか」だけでなく、「人間として何を大切にするか」を問われています。
今回は、私自身の体験を通して考えたことをまとめました。
AIが生み出す“驚きのスピードと精度”
最近、GoogleのAIサービスGeminiを使って論文生成を試みました。
わずか5分で20ページを超える論文と60本以上の参考文献リストが生成され、その完成度に衝撃を受けました。引用や参考文献も整い、論理展開もしっかりしている。
従来なら膨大な時間を要した作業をAIは瞬時にこなしてしまいます。効率性という点では、もう人間の手作業では太刀打ちできない部分があると実感しました。
それでも人間に求められる力とは
ただし、AIが生成したものをそのまま使えばよいわけではありません。
そこに込められた意味や根拠を理解し、問いに応じて取捨選択するのは人間にしかできないことです。
AIの出力を「そのまま受け取る」のではなく、「自分の責任で吟味し、再構成する」姿勢が不可欠です。むしろAIが当たり前の存在となった時代には、思考のデザイン力や本質を見抜く力こそが人間に求められていると感じます。
AIと共に生きるために意識したいこと
AIを敵視するのではなく、積極的に使いこなすことが大切です。
実際、私もメールの下書きや資料の整理など、AIをすでに日常的に活用しています。問題は「AIを使うことそのもの」ではなく、「AIに使われてしまう」ことです。主体性を持ち、自分の軸をぶらさずにAIを取り入れることが、これからの教育者・研究者に欠かせない姿勢だと思います。
おわりに
AI時代を生きる私たちは、ただ知識を知っているだけでは通用しません。
AIの助けを借りつつも、自分の価値観や学びの方向性をデザインし、表現していく力がますます重要になっていきます。これからの教育や研究の現場は、AIと人間がどう協働するかによって大きく変わっていくはずです。今こそ、私たち一人ひとりが「AI時代をどう生きるか」を考えるときではないでしょうか。
ラジオ登録のご案内
今回ご紹介した内容は、有料音声配信「まるしん先生の教育ラジオ」にて詳しくお話ししています。
教育に携わる皆さんの心に寄り添うラジオ、ぜひご登録ください。
👉 ご登録はこちらから:
https://stand.fm/channels/61f12f0a299c4d50055459a8