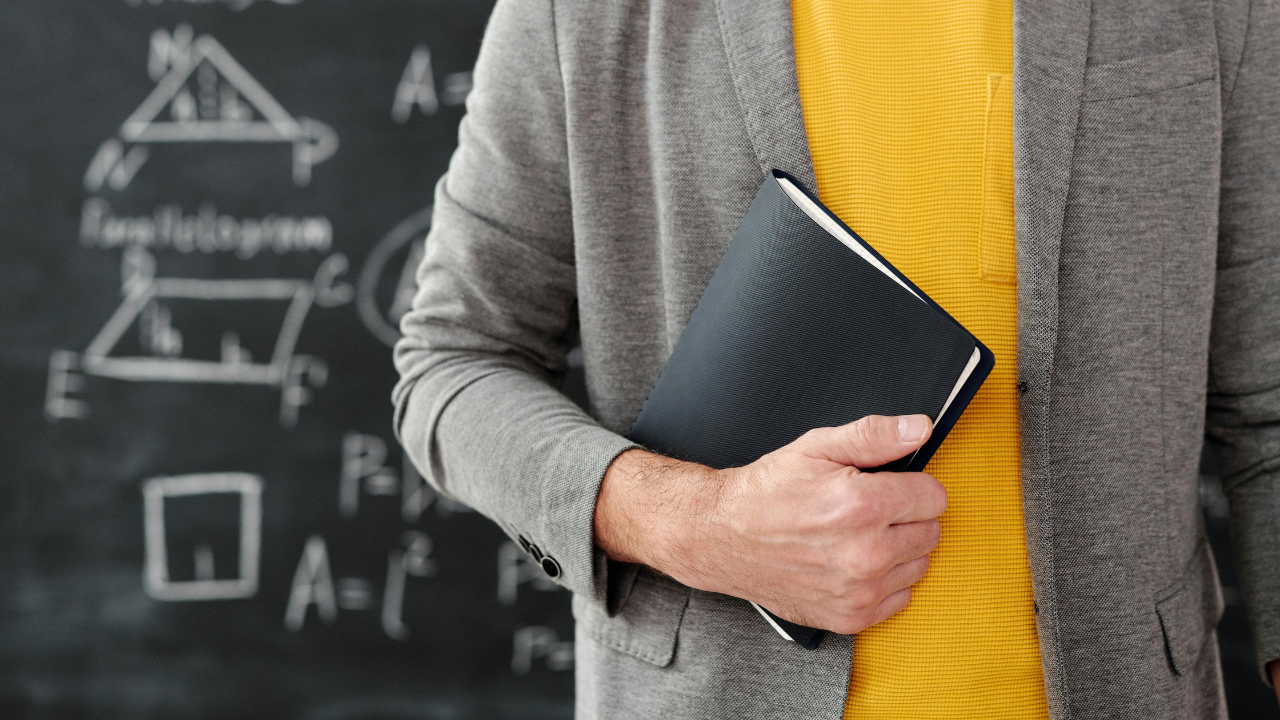はじめに
「教師の力量」と聞いて、どんな力を思い浮かべるでしょうか。
授業を組み立てる力、教材を読み込む力、子どもと関係を築く力…。
確かにどれも大切ですが、果たして力量はその先生“個人”の中だけに閉じているものなのでしょうか。
今回は、令和の時代に求められる教師の力量について、私自身が感じた気づきを整理します。
力量は「関係性の中」で生まれる
ある打ち合わせで「前回の授業をした先生に負けないように頑張ります」という言葉を耳にしました。その時、私は強い違和感を覚えました。教師の力量を「個人の能力」とだけ捉えると、どうしても比較や優劣に結びついてしまいます。しかし実際には、授業を支えるのはその人が築いてきた関係性や、周囲から受け取る助言も含めた“ネットワークの力”ではないでしょうか。
指導案検討会で見える「共同の力」
指導案検討会では、授業者に対して多くの助言や指摘が寄せられます。
従来なら「指摘が多い=準備不足」と見なされがちですが、実はその場で多くの意見を引き出せること自体が、その先生の力量の一部とも言えます。講師や同僚から助言を得られる関係性を築いていること、資料を丁寧に準備していること──それらもまた重要な力なのです。
OECD「ラーニング・コンパス」が示す視点
2015年にOECDが提示した「ラーニング・コンパス」には、個人の力を示す「エージェンシー」と、関係性の中で育まれる「共同エージェンシー」の概念が紹介されています。
授業づくりを一人の力に帰するのではなく、関係性の中で構成されるものとして捉える。
この視点は、令和の時代における教師の力量を考えるうえで欠かせない要素だと感じています。
おわりに
授業は決して一人でつくるものではありません。
周りの人の知恵や力を受け取りながら、それを自分の力に変えていく姿勢こそが、令和の時代に求められる教師の力量ではないでしょうか。教師同士がつながり合い、共同で学びを創る文化を築くことが、これからの教育を支える大きな力になるはずです。
ラジオ登録のご案内
今回ご紹介した内容は、有料音声配信「まるしん先生の教育ラジオ」にて詳しくお話ししています。
教育に携わる皆さんの心に寄り添うラジオ、ぜひご登録ください。
👉 ご登録はこちらから:
https://stand.fm/channels/61f12f0a299c4d50055459a8