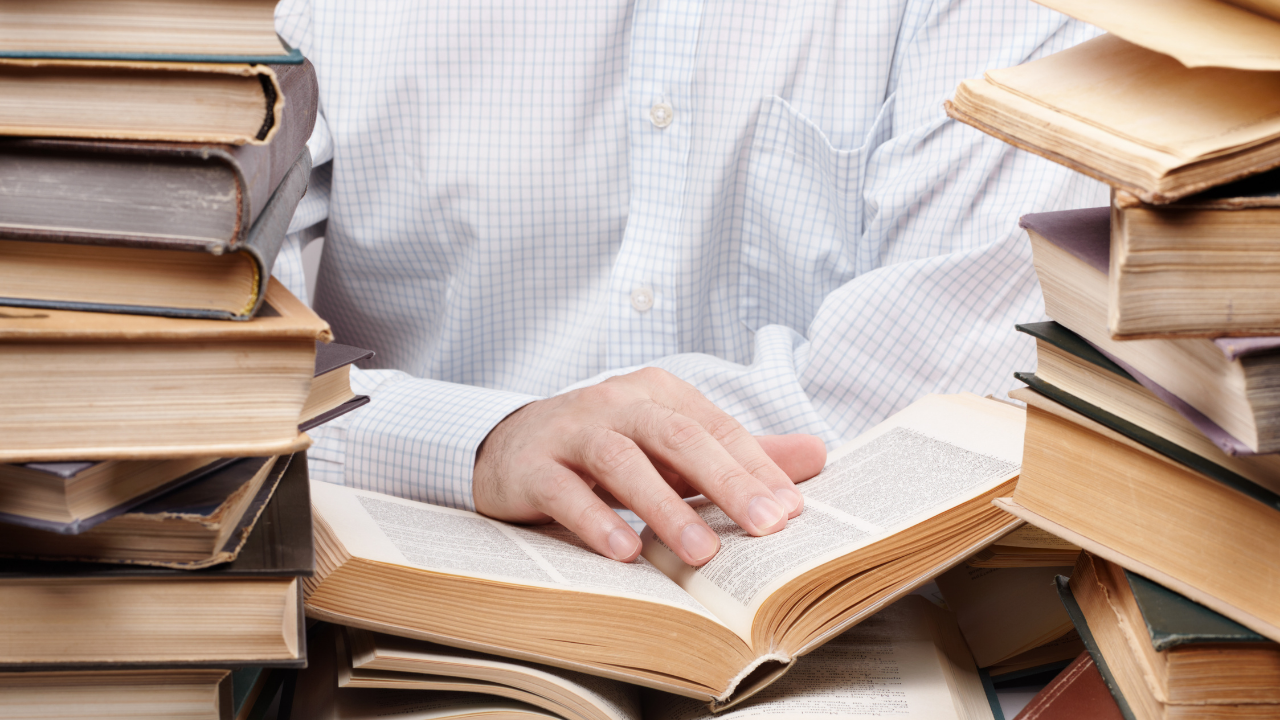はじめに
博士課程の準備を進める中で、「研究者とは何をすべき存在なのか」という問いに向き合うことが増えました。研究計画書づくりの難しさや社会の変化を踏まえながら、研究者の役割について考えてみます。
計画を突き詰める難しさ
研究計画書づくりは、一見地味な作業の連続です。テーマを具体的に突き詰め、必要な先行研究を調べ、論理を積み重ねていく。時間も労力もかかりますが、この過程を通じて自分の研究の立ち位置が明確になっていきます。
多様化する社会に対応する視点
今の社会は、多様な価値観や背景を持つ人々が共に生きる時代です。研究者は、その変化を捉え、教育や社会の課題に光を当てる存在でなければなりません。現状をただ評価するだけではなく、「ここが足りない」と指摘することにこそ意味があります。
提言することの意義
研究者の役割は、単に知識を蓄積することではありません。
教育制度や教科書、学習環境の改善点を見つけ出し、未来への提言を行うこと。それが、現場を支える教師や子どもたちに還元されていくのです。研究と現場をつなぐ存在であることが、研究者の使命だと感じます。
おわりに
研究者は「評価者」であると同時に「提言者」であるべきです。現場と学問を結びつけながら、社会の未来を少しずつ変えていく。その歩みを続けることこそ、研究者に与えられた大切な役割だと改めて思います。
ラジオ配信についてのお知らせ
これまで「まるしん先生の教育ラジオ」(stand.fm有料チャンネル)として配信してきましたが、今後は Voicyでの配信に切り替えていきます📻✨
『まるしん先生の道徳チャンネル!!』では、子どもたちの声を大切にした道徳授業づくりの工夫や最新の研究・実践を、より多くの先生方にお届けしていきます。
日々の授業づくりに役立つヒントを“すきま時間に耳から学べる”番組です。
ぜひフォローして、毎日の配信をチェックしていただけたら嬉しいです😊
👉 Voicyはこちら:
https://voicy.jp/channel/916314