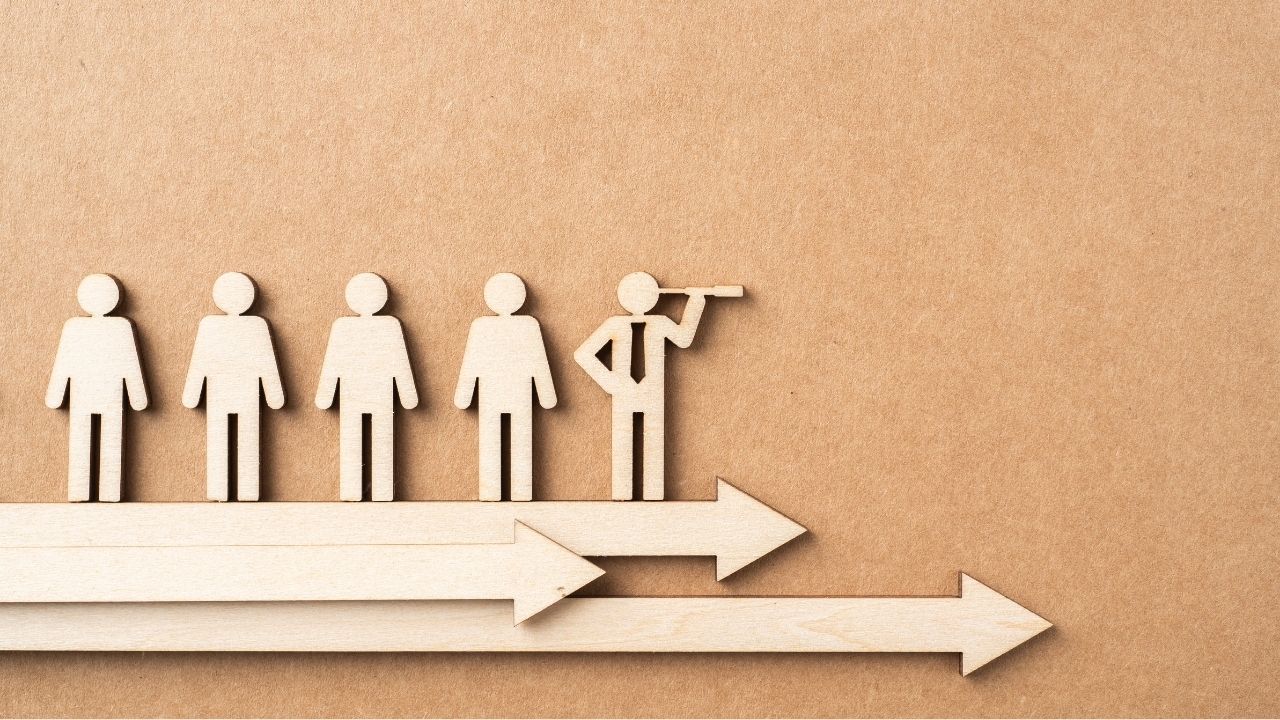はじめに
「担任がずっと一人でクラスを見続けることに限界を感じる」
そんな現場の声が増えてきました。
教員の働き方改革や、多様な教育ニーズに応える方法として、
「チーム担任制」や「教科担任制」が注目され始めています。
でも、本当に大切なのは──
仕組みを入れる前の“土台づくり”かもしれません。
オランダの学校で見た「働き方の柔軟さ」
以前訪れたオランダの学校では、
週5日勤務の先生がほとんどいませんでした。
週3〜4日勤務の先生が多く、
「今日は誰が担任か」が学校全体で共有されていました。
そのために、チーム担任制が自然と根づいているのです。
そこには、先生不足を背景にした
“先生が働きやすい環境を整える”という前提がありました。
「チーム担任」が成立するための鍵
日本でも、担任を複数人で分担する取り組みが一部で行われています。
しかし、そこでよく聞かれるのが――
「引き継ぎが大変すぎる」という声。
なぜ大変なのか?
それは、おそらく“共通言語”がないからです。
「共通言語」がある学校は、ブレない
オランダの学校では、たとえば「ピースフル・スクール・プログラム(PSP)」という
明文化された指導理念とスキルが、全教員に共有されていました。
その研修を通して、先生たちの中に
「私たちは、こういう視点で子どもに関わる」
という共通理解が根づいているのです。
だからこそ、曜日ごとに担任が変わっても
子どもたちが受ける指導の“軸”はブレません。
形だけの「分担」は、逆にしんどくなる
もし共通言語がないままチーム担任を導入すれば、
・先生によってルールが違う
・目指す方向がバラバラ
・引き継ぎのたびにトラブルが起き
ということが現実になってしまいます。
その結果、むしろ教員の負担が増えてしまうかもしれません。
教育の方向性が問われる時代に
「教科担任制」「チーム担任制」は、
単に業務を分担するだけの話ではありません。
学校として何を大切にしたいのか?
子どもたちに、どんな力を育てたいのか?
その“教育の軸”が共有されてこそ、チームでの教育が機能します。
導入の前に、問い直したいこと
これからの時代、ひとりの担任でクラスを見続ける体制には
限界があるのかもしれません。
だからこそ、体制を変える前に、こう問いかけてみてください。
- わたしたちの学校は、どんな力を子どもに育てたいのか?
- そのために、先生たちはどんな視点で関わっていくのか?
その答えを、「共通言語」として可視化すること。
それが、これからの教育チームにとっての基盤になるはずです。
ラジオ登録のご案内
今回ご紹介した内容は、有料音声配信「まるしん先生の教育ラジオ」にて詳しくお話ししています。
教育に携わる皆さんの心に寄り添うラジオ、ぜひご登録ください。
👉 ご登録はこちらから:
https://stand.fm/channels/61f12f0a299c4d50055459a8