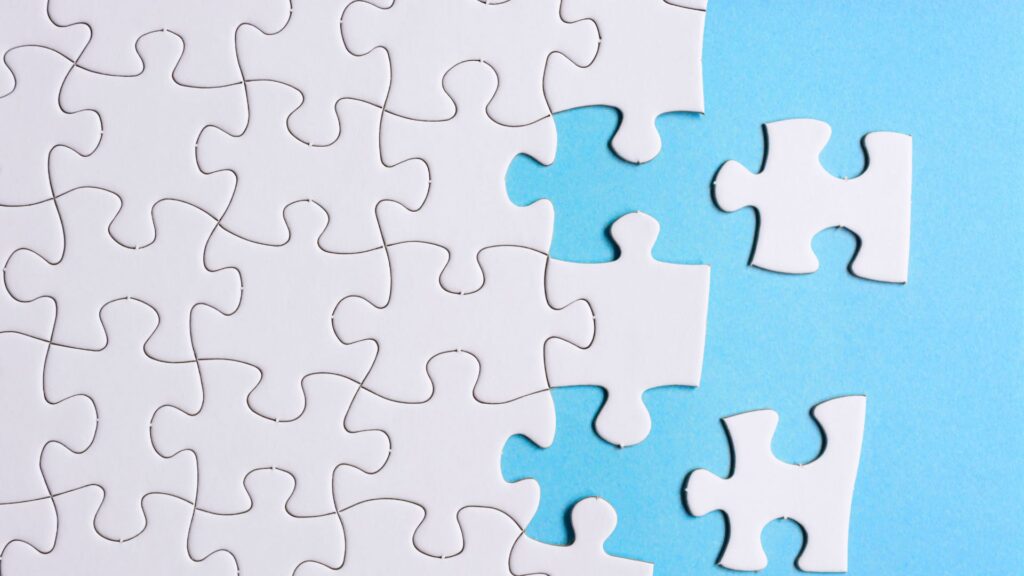ブログ– category –
-

信頼関係を技術で育てる|帯広での研修を終えて
冬休みの期間に、北海道・帯広市で「コミュニケーション」「学級経営」をテーマにした研修を行ってきました。 子どもたちとの信頼関係づくりは、教育の効果を高めるうえで欠かせない土台です。 ただ一方で、「信頼関係が大切」という言葉はよく聞くものの... -

プロセスと結果と
結果は、自分で完全に左右できるものではありません。 でも、そこに向かうプロセスは、自分で選ぶことができます。 結果は自分で決められなくても、その結果にたどり着くまでの積み重ねは、自分で決められる。 たとえば―― ・本を「5ページだけ」読んでみる... -

40代をどう生きるか。これからの自分と向き合った時間
昨日、とある先生からご連絡をいただき、「これからをどのように生きていくのか」「何がしたいのか」「自分の中にどんな目標を持つのか」と問いかけていただきました。誰かが自分のこれからについて本気で考えてくださっていることを、心からありがたく、... -

私たちは心理的安全性をどう実現するのか
【はじめに】 「心理的安全性」という言葉をよく耳にするようになりました。でも、ただ「安心して発言できる場」を目指すだけで、本当に人は成長できるのでしょうか?今回は、夏フェスでの学びを通して見えてきた“心理的安全性と成長の両立”について考えま... -

子どもたちが声を出せるようになる3つのワザ
【はじめに】 授業中、子どもたちが自信をもって声を出せていますか?「質問できる学級」を目指すには、その前段階として“声を出す力”が欠かせません。今回は、子どもたちが安心して声を出せるようになる3つのワザを紹介します。 【】 まず大切なのは、声... -

みんなの中で声が出せる指導を
【はじめに】 「質問できる学級をつくる」と聞くと、難しそうに感じませんか?でも、問いを持つ前に必要なのは、子どもたちが“安心して声を出せる”ことです。今回は、質問文化の土台になる「声の指導」について考えます。 【】 「何でもいいから質問してみ... -

フリートークをやってみよう
【はじめに】 授業の中で子どもたちが“自由に話す”場面をつくれていますか?ペアトークやグループトークは定着してきましたが、今回はその一歩先。「フリートーク」という形で、より自然な対話を生み出す方法を紹介します。 【】 “フリー”とは「どこで話し... -

時間と場所の影響力を考える
【はじめに】 長期休暇の期間、少しゆっくり過ごせると思いきや、実際には仕事や研修、打ち合わせで慌ただしく過ぎていく日々。そんな中で改めて感じたのは、「時間」と「場所」が人の思考や行動に与える影響の大きさでした。 【】 普段の仕事では、朝の電... -

グループトークを使う場面とは
【はじめに】 ペアトークは授業の導入でよく使われますが、では「グループトーク」はどんな場面で効果を発揮するのでしょうか。今回は、ペアトークとの違いと、グループトークが生み出す学びの深まりについて考えます。 【】 ペアトークはテンポがよく、ク... -

研修会で得た道徳授業の課題
【はじめに】 先日、平方で行われた研修会で道徳の模擬授業を行いました。「吹き出し君」というツールを使い、先生方からリアルタイムで意見を集めながら授業を進める形です。約100名の先生方から得られた反応の中に、改めて考えさせられる課題がありまし...