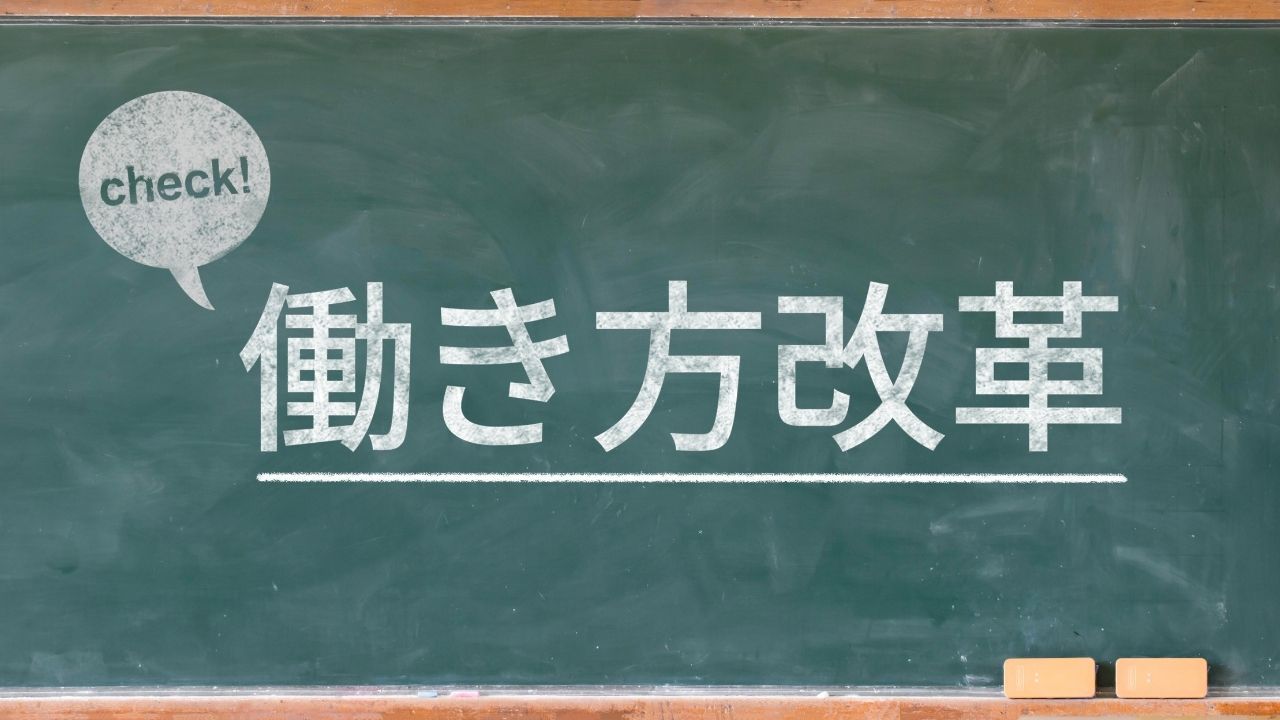はじめに
働き方改革を考えるとき、「授業は先生がすべて行うもの」という前提に縛られていないでしょうか?
この構造にメスを入れなければ、学校現場の働き方改革は根本的に進みません。
今回は、日々の授業のつくり方や子どもとの関わり方から、具体的に改革を進めるヒントを考えてみました。
全部を背負わず、子どもたちと“役割を共有”する
教員の仕事は、大きく分けて「授業・校務・保護者対応」の3つ。
中でも“授業”は教員が一手に担うものとされがちですが、本当にそれで時間も体力も持つでしょうか?
私自身、「1人一役当番制」を取り入れ、子どもたちに任せられる仕事はしっかりと任せる仕組みを整えました。
その結果、子どもたちは自分の役割を理解し、想像以上に意欲的かつ責任を持って動いてくれるようになりました。
「自分がやるよりもスムーズだった」
そんな経験が、役割を手放す勇気と実感につながりました。
「教える」と「任せる」のバランスを見極める
教員の時間とエネルギーには限りがあります。
だからこそ、教えるべきところと、子どもに任せてよい部分を意図的に整理して授業設計を行うことが大切です。
たとえば「学び合い」の要素を取り入れた授業では、子どもたちの力で課題をクリアしていく場面も多く見られます。
その間、教員は別の業務に取り組んだり、教室全体を俯瞰したりと、限られた時間を有効に活用することができます。
「先生がすべて引っ張る授業」だけが、良い授業とは限らない──
その考え方の転換が、働き方改革を進める一歩になります。
子どもの力を信じることが、改革の第一歩
掃除、準備、掲示物の張り替え、教具の管理──
こうした日常業務の多くは、子どもたちが十分に担える領域です。
私は教員3〜4年目に当番制を導入して以来、
「子どもの方が意欲的で、先回りして動いてくれることも多い」と実感してきました。
一人で背負い込まず、学級経営を“共につくる”姿勢が、働き方にも好循環をもたらしてくれます。
おわりに:意識を変えれば、時間はつくれる
結局のところ、働き方改革は“仕組み”だけでなく“意識”の変化が出発点です。
「45分すべてを先生が担う必要はない」
「子どもたちと役割を分け合えば、時間は生まれる」
そんな視点で日々の授業や関係づくりを見直すことで、現場の負担感は確実に変わっていきます。
「改革」と聞くと大きな取り組みに思えるかもしれませんが、まずは目の前の授業から。
そこにこそ、明日へのヒントが詰まっているのではないでしょうか。
📻 まるしん先生の教育ラジオ、聴いてみませんか?
今回ご紹介した内容は、
日々の実践や研究の気づきをリアルに語る
有料音声配信「まるしん先生の教育ラジオ」でお話ししています。
授業づくりに悩んだとき、
キャリアのヒントが欲しいとき、
ほんの少し立ち止まりたいとき──
先生方の毎日にそっと寄り添うラジオです。
移動中やすきま時間に、ぜひ耳を傾けてみてください。