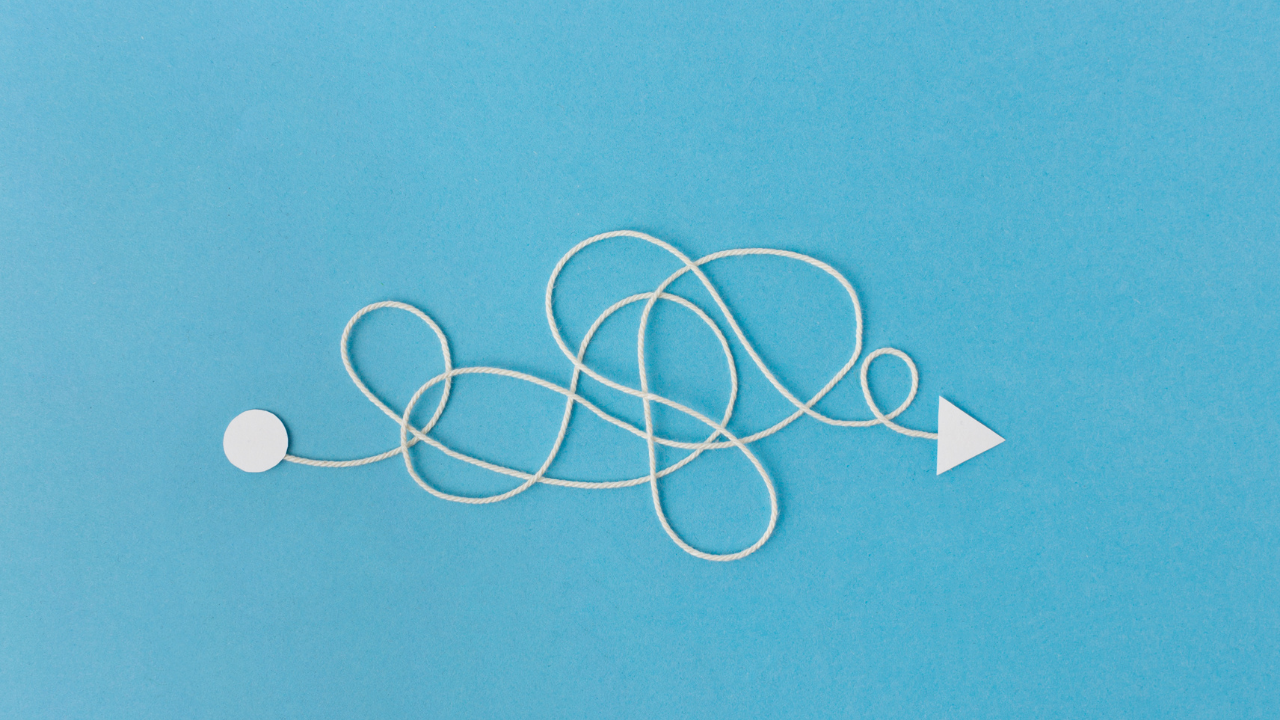はじめに
学校現場は慌ただしい日々が続いています。
私自身もICT担当として新たな立場で動き出し、日々さまざまな課題に向き合っています。
そんな中で実感しているのが、「問題の根っこを見ているか?」という問いの重要さです。
立て続けに起きたシステムトラブル
少し前の出来事ですが、保護者との連絡ツールに大きなエラーが発生しました。メッセージが送れない、サーバーが重すぎて動かない…。その対応に追われる中で、翌日にはまた別のトラブルが。ある先生だけがメッセージを送れないという事態です。
こうした“後手後手の対応”を続けていると、日々の予定が崩れ、仕事が雪崩のように押し寄せてきます。まさに「いたちごっこ」。この構造から抜け出すには、目の前の現象ではなく、その背景にある根本原因=根っこを見なければなりません。
モグラたたきになっていないか
この感覚、実は学級経営や授業づくりでも同じです。
子どもへの声かけを何度繰り返しても変化が見られない。保護者対応が何度もやり直しになる──そんなときは、表面的な現象にとらわれず、「そもそもなぜこの行動が起きているのか?」と一段深く掘り下げて考える必要があります。
根っこを見なければ、永遠にモグラたたきを繰り返すことになります。
変化には“痛み”も伴う
根本原因にたどり着くと、そこから先は大変です。
資料をつくる、人と調整する、立場のある人と話す──普段なら避けたくなるような労力が必要になります。ときには、「今のやり方を変える」「切る判断をする」など、痛みを伴う決断も必要になるかもしれません。
でも、その一歩を避けてしまえば、問題は形を変えて繰り返すだけ。根っこを断たなければ、本当の意味での解決にはならないのです。
授業づくりにも通じる視点
この考え方は、授業づくりにも応用できます。
「子どもたちが学びに向かわない」──それは、もしかすると授業そのものが今の時代とズレているのかもしれません。一斉指導だけでは届かない、過去の方法論が今には合っていない──そんな根っこに目を向ける視点が求められています。
おわりに
「なんだかうまくいかない」そんなときこそ、表面だけで判断せずに“根っこ”を探してみること。
そして見つけたなら、そこから目をそらさず、時間と労力をかけてでも向き合っていくこと。
それが、持続可能な問題解決への道だと、私は信じています。
📻 まるしん先生の教育ラジオ、聴いてみませんか?
今回ご紹介した内容は、
日々の実践や研究の気づきをリアルに語る
有料音声配信「まるしん先生の教育ラジオ」でお話ししています。
授業づくりに悩んだとき、
キャリアのヒントが欲しいとき、
ほんの少し立ち止まりたいとき──
先生方の毎日にそっと寄り添うラジオです。
移動中やすきま時間に、ぜひ耳を傾けてみてください。